e-コンシェルジュのサービスを思いついたとき、
私は、駅のプラットホ-ムに立ちすくんだのを覚えている。
これは面白い!と。
このページでは、e-コンシェルジュサービスに注ぎ込んだ、
我々の溢れんばかりの「熱き思い」と、
その「コンセプト」をご紹介します。どうぞコーヒーブレイクにご一読下さい。

サービス誕生のキッカケとなった
静岡県三島市の
「ケーブル買いに走り事件」
20年ほども前、我々は大手コンピュータメーカーから「個人向けパソコンセットアップ」という業務を受け持っていた。
自分ではパソコンの設置や設定ができない個人ユーザー宅に訪問し、ユーザーに代わってパソコンを組み立て、
インターネットをつなげてくるのである。
富士山麓にある静岡は
三島市のご年配の女性から依頼
あるとき、富士山麓にある静岡は三島市のご年配の女性から依頼が入った。
『お孫さんとメールで会話がしたい』
しかし自分でパソコンなどの組み立てはとてもできず、私どもへの依頼となったワケだ。
が、作業も無事に終わりかけたとき、パソコンと一緒に買ったプリンタのケーブルが無いことに気が付いた。
本来なら、我々のセリフは
「 では、ケーブルはプリンタを購入されたお店でまたお買い求め下さい。
その後、もしご要望あれば私どもが参ります。ただし有料になりますが… 」
と言い残して帰るはずだった。
だがそのとき、作業スタッフは
「 いいです。私が今から買ってきましょう 」
と言って車を飛ばし、遠く山の麓の量販店までケーブルを買いに行ったというのだ。
お客様であるこのご年配の女性が、一日でも早く、お孫さんとメールができるよう、
作業スタッフは、その親切心だけでケーブルを買いに走ったそうだ。
そして作業スタッフは、お客様からケーブル代金を受け取り、無事にすべての作業を済ませ、ユーザー宅を後にした。
本当なら、この心温まる話はここまでである。
だがこの後、とんでもない展開が待っていた。
e-コンシェルジュサービスの
原型となるビジネススタイル
数日後、私はこの仕事の元請けである大手コンピュータメーカーのリーガル部門(法務部)から
呼び出しを受けることになった。
なんと、このケーブルを買いに走った美談が大問題となっていたのだ。
「 サービスメニューに無いことをしてもらっては困る 」
と言うのだ。
お客様に代わって部品を買いに走るというのは、一歩間違えればクレームの対象にも変わることがある。
つまり “ 余計なことはするな ” との叱責だ。
確かにそうだろう。
良かれと思ってやったお節介は、もし不測の出来事があったとき、我々の側に責任を転嫁してくるユーザーは個人客に多い。
我々も青臭い理論でビジネスをしているわけではない。
そこは割り切って、ユーザーには少し冷たい対応をしなければいけないこともある。
それは痛いほど分かっていたつもりだ。
だが、呼び出された帰り道、悲しい気持ちで足が重くなった。
聞くところによると、このご年配の女性、作業スタッフのあまりの親切に感激し、
元請けコンピュータメーカーの社長宛に、わざわざ「お礼状」をしたためたことから、この事件が発覚したそうだ。
なんと言う皮肉だろう。
「 お客様がこんなに喜んでいるのに 」
と思うと、
つくづく我々のコンピュータ業界の掟である【 線引きのスタンス 】 に嫌気が差した。
「 ウチはここまでしかやりません 」
「 それは私どものせいではないです 」
「 それはお買いになったお店に言って下さい 」
というセリフを、これまで幾度吐いてきただろう。
そんなことを考え込んでいた地下鉄のプラットホームで、フっと閃くものがあった。
「 待てよ…。この杓子定規な線引きを、ビジネスにできないだろうか…」 と。
みんなが線引きをする。
そこに ” 誰もやらないスキ間 ” が生まれる。
ユーザーはその ” スキ間 ” を埋めて欲しいのではないのか?
しかしそこにはリスクも潜んでいる。では、どうやってビジネスにする?
この瞬間、e-コンシェルジュサービスの原型となるビジネススタイルが、頭の中をグルグルと回り始めた。
私は、地下鉄のプラットホームで何本かの電車を見送った。
よし!ならば
「三河屋のサブちゃん」を
目指そう。
サザエさんに登場する ” 三河屋のサブちゃん ” を知らない人はいないだろう。
我々はこの ” 三河屋のサブちゃん ” をe-コンシェルジュサービスの目指す「サービススタイル」と定めた。
サザエさんで、昔ながらの 【 出入りの御用聞き 】 を演じるのがサブちゃん。
いつも絶好のタイミングで現れるサブちゃんにサザエさんは言う。
「 ちょうど良かった。お醤油が切れかけてたの。 そうね、お味噌もいつものを持ってきてよ 」 と。
サブちゃんは、
「 ああ、いつものですね。分かりました。あ、サザエさん、手に持ってる手紙、出しときましょう。帰りにポストの前を通るし 」
「 そうそう、タラちゃんが裏の空き地で転んで泣いてましたよ 」 と。
この、サザエさん一家を知り尽くすサブちゃんこそが、e-コンシェルジュの原型となる。
磯野家を知り尽くす
「三河屋のサブちゃん」が
e-コンシェルジュの原型に
サブちゃんは磯野家を隅々まで知っている。
何も言わなくとも、一度に頼むお味噌の量、どんなお味噌が好きなのか、そろそろお醤油が切れかけていること、
波平が最近塩分を気にしていることも。
サブちゃんは頼まれなくても、磯野家にピッタリの品を、ピッタリのタイミングで届けに来てくれるのです。
そして、余計なお節介はサブちゃんの信条でもあります。
サザエさんは、駅前のスーパーでお醤油を買った方が安いのを知っています。
でもサザエさんは、サブちゃんにお醤油を頼みます。
サザエさんは、どうやら安いだけで買う先を決めているのではなさそうです。
お醤油という商品の付加価値だけでは得ることのできない、
線引きと線引きのスキ間に、明らかに存在するであろう付加価値を、
実は、まだこの時代にも必要とするユーザーがいることを、我々は追い求めることにしたのです。
そしてついに見つけたのです。
「業務」の
アウトソーシングではなく、
「社員」の
アウトソーシングをする。
大手企業は、自社内に 『 IT部門 』 を持っています。
ですから彼らは、ITのパーツだけを欲しがります。高い技術だけをお金を払って買おうとします。
自分達だけでそれらを効果的につなげて活用することができるからです。
一方、中小零細企業は、ITパーツだけを届けてあげても、それを上手く使っていく技量を持っていません。
中小零細のユーザーは、そこを埋めて欲しいのです。
技術的にも分からない。人もいない。ITに詳しい社員を雇うこともできない。ITの仕事が毎日あるワケでもない。
しかし、もはやITがなければ仕事ができないのです。
そこで中小零細のユーザーは、ITベンダーに 「 パーツをつなげて欲しい 」 と頼むのですが、
多くのITベンダーは 「 私達がするのはここまでです 」 と、本来、ユーザーがすべき範囲には手を出してくれないのが現実です。
責任が取れないからです。
でもユーザーは、そこを誰かにやってもらわないと前に進めません。
そこで我々は、 「 ITベンダーがしない部分をする 」 を、コアサービスにしようと考えたのです。
これが 【 e-コンシェルジュサービス 】 なのです。
e-コンシェルジュサービスの正体は 【 社員のアウトソーシング 】
まず、請負業務をしないことにしました。 例えば、
「 社内のパソコンを無線LAN環境にして欲しいので見積もってよ 」
という仕事は請けないようにしました。
これをすると例えば、事務所の構造によって電波の飛ばない場所があったりしたときに、
「 つながらないのは私達のせいではないです 」
で引き上げてしまうからです。
ユーザーは仕方なく納得しますが、その後、どうすればいいのか立ち往生してしまいます。
まさかビルの管理会社に後を頼めるはずもありません。
では請負契約ではなく、人材派遣で引き受ける手はどうでしょう。
確かに派遣されてきた技術者は、請負ではできなかった 【 立ち往生の事情 】 にも果敢に挑戦してくれるかもしれません。
ですが、派遣の時間が過ぎてしまえばその技術者は 「 引き上げます 」 と言って、帰ってしまうではありませんか。
これも “ 時間の線引き ” です。
ユーザーはやはりここでも立ち往生してしまうのです。
ではどうすれば良いでしょう。
結局これは、ユーザーがするしかないのでしょう。つまり、社員でしかできないのです。
なぜなら、社員は線引きなどしない(できない)からです。
くどいようですが、e-コンシェルジュサービスは、
このITベンダーや人材派遣会社から放り投げられた “ 線引きの向こう側 ” を担当したいのです。
そうです。e-コンシェルジュサービスの正体は 【 社員のアウトソーシング 】 だったのです。
請負業務でもなく、人材派遣でもなく、ある決められた業務のアウトソーシングでもなく、
【 社員のアウトソーシング 】 を作ってやろうと思ったのです。分かりにくいかもしれません。
ですが、サザエさんの手にあった手紙の投函までを引き受けるサブちゃんのような行動も、
社員がするなら何の違和感もないではありませんか。
一人の社員を複数企業で
シェアをする。
これがe-コンシェルジュの
廉価の仕組み。
しかしここで大きな問題にブチ当ります。
社員のアウトソーシングって、いったいいくらかかるのでしょう。
ITの専門家は、極めて人件費の高い人種です。
そんな人種に、社員のアウトソーシングを頼めば、費用は小さくありません。
ましてや中小零細の法人に、それを負担させることなどできるのでしょうか。
この難題をクリアできなければ、e-コンシェルジュは実現できません。
考えに考え、そして、ある面白い仕組みを思いつきました。
1人のIT専門家を、
複数の企業でシェア
1人のIT専門家を、複数の企業でシェアするのです。
妙案でした。
1人の社員が、複数の企業に所属するなんて、聞いたことがありません。
ですが、中小零細企業に、毎日、そんなに多くのIT業務があるとは思えません。
ならば複数の企業で、1人をシェアして使っても、十分に足りるはずだと考えたのです。
このe-コンシェルジュサービス。
人材派遣ではないのですから、各社のシェアの時間を一定にする必要はありません。
来て欲しいときにだけ来てくれて、仕事が無いときは、別の会社に行ってしまっている社員なのです。
でも、社員なのですから、何度仕事を依頼しても、何回来てもらっても構わないのです。
つまり、オンデマンド(必要なときに必要な分だけ)の社員なのです。
いかがでしょう。面白い仕組です。
高い人件費を、みんなで負担して安くしてしまうのです。
むろん、複数社でシェアをしているのですから、ウチにだけ来い、ウチにずっと居ろ、ウチに先に来い、なんてのはNGです。
e-コンシェルジュには
守備範囲だけを決めました。
これが唯一の制約です。
さてついに、オンデマンド社員の仕組みが出来上がりました。
ですが、このe-コンシェルジュにも守備範囲だけは必要でした。
どういうことか説明をします。
コンシェルジュに依頼できるのは
【 日常的に発生する業務まで 】
何度でも仕事を頼める。何回でも来てもらえる。
このe-コンシェルジュの自由度を広義に活用すれば、
コンシェルジュを長く事務所に座らせ、本来は数百万円もするホームページを 「 そこで作れ! 」 と
命じることも可能となってしまいます。これはさすがに無理があります。
なので、あくまでコンシェルジュに依頼できるのは
【 日常的に発生する業務まで 】という範囲だけを定めることにしました。
例えば、 「 急にネットワークがつながらなくなった。復旧を頼む 」
というトラブルは日常的に起こりうる事象です。
例えば、 「 新人が1人入社するので新しいパソコンをLANに加えて欲しい 」
という依頼も日常的な事象でしょう。
例えば、「 社員が外出先でメールを確認したいんだけど、どうすればいい? 」
といった相談も日常ではよくあることでしょう。
日常業務の依頼は、何度でも、何回でも依頼しても構わないのです。
これらの日常にあるIT業務は、すべてコンシェルジュの月額の料金範囲で依頼ができる、としました。
非日常の業務
一方、【 非日常の業務 】とはどんな業務なのでしょう。
例えば、「 社員全員のパソコンを入れ替えて欲しい 」などがそれです。これは一人ではできません。
「 全国にあるすべての支店をVPNでつないで欲しい 」や
「 Exchangeサーバーを立ち上げて欲しい」などもそれに当たります。
これらは本来、多くの労力がかかったり、非常に高い技術スキルを求められる業務で、
一応に、高額の報酬が要求される業務です。
これらは、日々、日常的に発生する業務というより、IT化計画の中で推進される業務であり、
また、こういった 「 本来はITベンダーに依頼する 」 というSPOT的な業務は、
コンシェルジュにとって 【 非日常の業務 】 と定義することにしました。
この定義については、「よく分かりにくい」という指摘ももらいます。
そんなときは、次の例をあげて説明をしています。
例えば、事務所内で引越しがあったとします。
1人の社員が異動となり、2Fから3Fに引越しをしようとしたとき、
これぐらいならば自分達だけ(社員だけ)でやってしまうでしょう。
ところが、2Fの部署と、3Fの部署の総入替え、となるとどうでしょう。
これは、社員だけでできる範囲を超えています。
会社はこの引越しを、きっと業者に依頼するはずです。
いかがでしょうか。前者が日常業務で、後者が非日常業務です。
かなり 【 アバウトな定義 】 なのかもしれません。
が、これは(言葉はやや不適切ですが)e-コンシェルジュサービスの 「 何度でも依頼できる 」 という特徴を、
乱用されないために設けられた、このサービス唯一の制約なのです。
仕上げは【セカンド】という
奇想天外な仕掛け。
これがコンシェルジュの品質と熱意を生み出した。
さて、高い人件費であるIT専門家を安く、そしてスキ間を埋めてくれる仕組みは出来上がりましたが、
この仕組みには、実は大きな欠点がありました。
コンシェルジュは社員のアウトソーシングなのですから、呼ぶ回数に制限はなく、
日常の業務の範囲であれば、何度でも対応をしてくれるサービスです。
しかしこれは、コンシェルジュにとって、呼ばれれば呼ばれるほど、損をする仕組みになっています。
e-コンシェルジュサービスの料金は固定額です。
ということは、何度呼ばれても、もらえる額が同じなら、コンシェルジュは呼ばれる回数が少ない方が得をすることになります。
一番ありがたいのは、まったく呼ばれず、月々の報酬だけをもらうことでしょう。
ですが、そんなことを願っていては、良い仕事ができるはずがありません。
これは、最後に立ちはだかった難テーマとなりました。
【 固定の報酬額 】 と
【 呼び出し無制限 】
【 固定の報酬額 】 と 【 呼び出し無制限 】。
この相反目する2つの要素の、両方を叶える手段はないだろうか。
これもやはり考えに考えた挙句、ある、とんでもない奇想天外な仕掛けにたどりつきました。
サービス品質の低下を防ぐどころか、コンシェルジュがやる気満々に仕事に臨む、という前代未聞の仕掛けでした。
これこそ、e-コンシェルジュサービスを実現させた、最大のコアトリックでした。
我々はこの仕掛けのことを 【 セカンド 】 と呼んでいます。
図1は、世間一般に見られるビジネスの商流です。
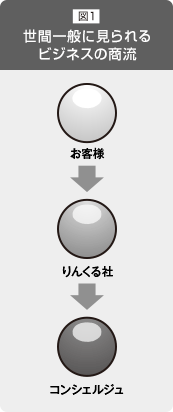
e-コンシェルジュサービスの契約は、お客様とりんくる社で結ばれます。
そしてりんくる社は、その業務を、コンシェルジュに委託します。図1の通りです。
コンシェルジュは、全国に所在する個人事業主であり、りんくる社の社員ではありません。
図を見て分かる通り、コンシェルジュは、りんくる社の下請けとなっています。
下請けは、言われたことしかしないのが当たり前。
言われた以上にしちゃうと、損をした気分になってしまうのが、悲しき下請け稼業です。
これでは、りんくる社は毎日、コンシェルジュが熱意をもってお客様に接しているかを疑い、見張らければなりません。
そんな関係で、コンシェルジュサービスが円滑に回るはずもありません。
そこで図2の関係です。
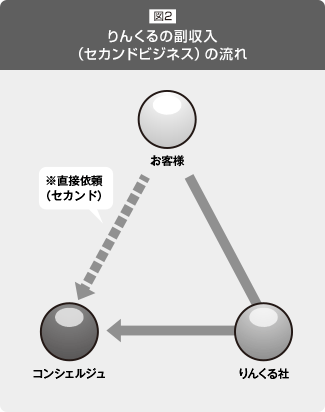
コンシェルジュは、お客様から直接、仕事を引き受けています(点線の矢印)。
下請けが元請け(りんくる社)をスッ飛ばし、直接、お客様と取り引きするなど、通常、あってはならないことです。
これはビジネスの厳しい掟でもあります。
が、それを推奨しているのが、このe-コンシェルジュサービスなのです。
コンシェルジュにとっては、りんくる社から支払われる固定報酬だけでなく、
お客様と直接、ビジネスをすることで得られる 【 副収入(セカンドビジネス)の流れ 】 を作ったのです。
お客様からの仕事の依頼の中には、 『 非日常の業務 』 があります。
非日常の業務は、別料金を頂かなくてはなりません。
例えば、ホームページを作って欲しい、サーバーを構築して欲しい、毎日来てデータを入力して欲しい、などなどです。
e-コンシェルジュサービスでは、これら 『 別料金の業務 』 だけは、
お客様から、コンシェルジュに直接依頼することを認めたのです。
りんくる社は、日常業務の 【 e-コンシェルジュサービス 】 だけに専念し、非日常業務は 【 セカンド 】 と位置づけたのです。
直接取引 【 セカンド 】こそ、
やる気を生み出す仕掛け
この仕組みのお客様メリットは「安く頼める」ということに尽きます。
別料金がかかってしまう非日常の業務が、
図1のように、お客様→りんくる社→コンシェルジュと流れた場合、りんくる社の取り分だけ高くついてしまいます。
だったら、どうせコンシェルジュがその仕事をするのであれば、
図2のように、お客様→コンシェルジュと、直接依頼できる方が安く仕上がるのです。
では、なぜこれが、コンシェルジュの高い品質と熱意を生み出すのでしょうか。
図1の下請け構造ではなく、図2のように直接取引ができる関係ならば、
コンシェルジュにとってお客様は、” 自分のお客様 ” にもなり得る存在です。
コンシェルジュは、お客様からの信用を勝ち取らなければ、セカンドは回っては来ません。
コンシェルジュは、懸命に、日頃の業務に精を出し、お客様から 「よし、君になら別の仕事も頼めそうだ 」 と思ってもらえないと、
セカンド(副収入)にたどり着けない仕組みなのです。
ですからコンシェルジュは、お客様に 【 直接取引の合格 】 をもらいたく、一生懸命に頑張るのです。
この一生懸命が、高い品質を生むのです。
コンシェルジュは、サボっていてはセカンドにはありつけません。
そればかりか、評価が低ければ、セカンド以前に、e-コンシェルジュサービスの契約さえ解消されてしまいます。
セカンドは、お客様、りんくる社、そしてコンシェルジュの3者が、互いにWIN-WINとなる、
世にも奇想天外な 【 やる気を生み出す仕掛け 】 となったのです。
ちなみに、お客様にとって、別料金となる非日常の業務を、
図2のように、コンシェルジュに直接依頼するも、やはり図1のように、りんくる社を通すも、
まったく別のITベンダーに依頼するも自由です。
コンシェルジュは、直接依頼が自分に来るように、ただ、頑張るのみなのです。
意図的グレーゾーンを持つ
不思議サービス。
これこそがe-コンシェルジュの真骨頂。
最後にもう1つだけ、面白いコンセプトを紹介します。
e-コンシェルジュサービスの
真骨頂。意図的グレーゾーン
【 意図的グレーゾーン 】 です。
例えば、サービス提供の時間帯です。
コンシェルジュを呼べる時間帯に、クッキリとした定めはありません。
契約時に、「 おおよそ平日の9時から18時ぐらいです 」 という言い方をします。
ですが、20時にコールがあって、そして体さえ空いているならば、
コンシェルジュはお客様の元に駆けつけるはずです。
決して「18時を過ぎているので行きません」なんてセリフは吐かないでしょう。
このアバウトさ、グレーゾーンこそがe-コンシェルジュサービスの真骨頂です。
意図的グレーゾーン。
なぜなら、コンシェルジュは御社の社員なのです。
社員ならば、どこの会社でも、少しぐらいのムリは
聞いてくれるのではないでしょうか。
e-コンシェルジュサービスは、多少のムリなど、
快く呑み込んでしまうサービスなのです。
そうです。三河屋のサブちゃんのように。
このe-コンシェルジュサービス。
世の中に、ありそうでありません。
不思議なサービスだと思われるかもしれません。
ならばどうぞ、e-コンシェルジュサービスをお試し下さい。
コンシェルジュは、そこで驚くべき品質と熱意を、
お客様に提供するはずです。
お約束します。




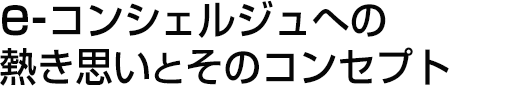
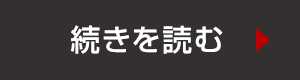
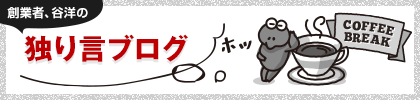






例えば、1人の社員を、10社でシェアをしたならば、
その社員は、それぞれの会社に
1時間ずつしか体を置けないかもしれません。
でも、1社の1日のIT業務量は、
その1時間で十分だよ。という発想です。